「何から始めればいいのか分からない…」築古の家を解体しようと考えたとき、多くの人が最初にぶつかる壁です。許可申請や近隣対応、工事中の流れまで、一度も経験がないあなたでも安心して進められるよう、全体像を明確にお伝えします。
目次
Toggle解体工事の基本手順と全体フローの把握

解体工事には「何から始めて、どこで終わるのか」が見えにくいことが多いですが、基本的には3つのステージ ― 事前準備、工事実施、工事後対応 ― に分かれています。
まず、施主が最も関与するのは「事前準備」にあたる段階です。
このタイミングで業者選定や見積もり比較を行い、近隣への挨拶、電気やガス・水道などライフラインの停止手続きなども済ませておく必要があります。
また、延床面積80㎡を超える場合は「建設リサイクル法」による届け出が必要になるため忘れずに。
次に「工事実施」では専門業者による解体作業のみならず、安全確保や廃材処理まで一連のフローで進みます。
具体的な手順としては以下の通りです。
- 外構(塀・庭構造物など)の撤去
- 足場設置および防音パネルによる養生作業
- 屋根や内装材(壁紙・建具など)の先行撤去
- 建物本体とその基礎部分の重機解体
- 埋設物確認後の整地と清掃
この間、施主が行う作業はほぼありませんが、不測のトラブル(埋設物発見・契約外作業など)対処のため、一定頻度で進行確認を行うとなお安心です。
最後に「工事後対応」です。
完了後は建物滅失登記を管轄法務局へ申請します。
これは施主責任で行う法的手続きであり、おおむね解体完了後1か月以内が目安です。
また、希望があれば地鎮祭や土地売却相談など次工程への準備に移ります。
以下が代表的な解体工事手順と各工程のおおよその日数感です:
| 工程名 | 施主の関与 | 代表的作業日数 |
|---|---|---|
| 外構撤去 | 無し | 1~2日 |
| 足場・養生設置 | 無し | 1日 |
| 屋根・内装解体 | 無し | 2~3日 |
| 建物本体解体 | 無し | 2~3日 |
| 基礎解体 | 無し | 1~2日 |
| 整地・完工 | 無し | 1日 |
スケジュール全体では、おおよそ木造住宅の場合7〜10日前後を想定しておくと妥当です。
雨天延期、地中埋設物など突発要素も加味し、一週間程度余裕ある計画を立てると安心ですよ。
解体工事前の準備手順と必要な手続き

解体工事手順の中でも、最もトラブルを避けるカギになるのが「着工前の準備」です。
まず施主が最初に行うべきなのは、信頼できる業者選びです。
住宅解体の準備としては、「業者探し → 現地調査による見積もり → 内容の比較検討 → 契約締結」という流れになります。
特に現地調査を行わずに見積もりだけ出す業者は、追加費用が発生するリスクがあるので注意が必要です。
家屋解体の流れとしてここで重要なのは、「契約内容に廃材処理・整地作業・追加作業時の対応」が含まれているかどうか確認することです。
契約後から実際の施工(解体工事施工方法)までには、施主による複数の準備が必要になります。
まず行政への届出として、延床面積80㎡以上であれば「建設リサイクル法」の対象となり、市区町村への事前申請を済ませなければなりません。
続いて必ず行うべき作業が、電気・ガス・水道などのライフライン停止手続きです。
これらは施主側で各会社へ連絡して廃止や一時停止を依頼します。
また、不用品や家具家電などもこの段階で片付けましょう。
残したまま施工日を迎えると、追加料金や工期延長に繋がります。
さらに、騒音や振動で迷惑をかける可能性があるため、近隣への事前挨拶も欠かせません。
必要に応じてお祓いなど儀式対応もこのタイミングで行います。
最後に解体業者と細かいスケジュールをすり合わせておくことで、梅雨や繁忙期でもゆとりある進行ができますよ。
以下は、家屋解体の流れで施主が最低限対応すべきチェック項目です:
- 電気・ガス・水道などのライフライン停止
- 近隣住民への事前挨拶
- 行政への解体届出(建設リサイクル法など)
- 不用品の撤去・片付け
- 解体業者との施工スケジュール確認
このような準備工程を丁寧に踏めば、解体工事やり方に対する不安も大幅に減りますよ。
解体工事中の施工手順と各工程の流れ

解体工事手順において、実際の工事中の作業は大きく5つの工程に分かれます。
解体工程の順番を正しく把握することで、何がどのタイミングで進行するのかを予測でき、思わぬトラブルや追加費用にも冷静に対応できるようになりますよ。
初日に行われるのは、屋根材や外装仕上げ材など露出部分の撤去です。
木造住宅解体段取りでは特に瓦やトタン屋根が多く、この作業だけで丸一日かかります。
続いて内装材 ― 天井・壁・床面や住宅設備機器など ― を取り外す作業へと移ります。
この段階では人力でも多くの作業が必要で、1~2日を要するケースが一般的です。
内装解体が終わるといよいよ本体構造の分解。
重機を用いた柱・梁・基礎など主要構造部分の搬出作業が中心となり、大きな騒音や振動が発生するため近隣との調和も重要です。
RC造解体工程や鉄骨系ビル解体工程の場合はこの重機フェーズが長引きやすく、作業は2~3週間におよぶケースも珍しくありません。
そして構造材撤去後は地中埋設物(古い配管・杭など)の確認工程が行われます。
ここで想定外の障害物が見つかった場合には追加対応が必要になるため、この工程も見逃せないポイントです。
最後は現場全体を清掃しながら廃材を回収・搬出し、整地作業まで一貫して完了させます。
不整地放置によって次フェーズ(建て替え・売却)への影響も出るため、仕上げまでしっかり監督しましょう。
以下に、代表的な解体工程ごとの内容とおおよその期間目安をまとめました:
| 工程 | 作業内容 | 所要期間(目安) |
|---|---|---|
| 屋根材撤去 | 瓦、トタンなど除去 | 1日 |
| 内装材撤去 | クロス・建具・配管など | 1~2日 |
| 重機解体 | 柱・梁など構造材解体 | 2~3日 |
| 地中物確認 | 地中配管・杭の有無確認 | 1日 |
| 廃材処分・整地 | ガラ収集・搬出・整地 | 1~2日 |
この流れを基準にして、木造住宅なら約7〜10日間前後で工事完了。
一方で鉄骨造やRC造の場合は構造強度からさらに時間が必要となり、おおよそ2〜3週間ほど見積もっておくと安心です。
解体工事後の処理と手続き
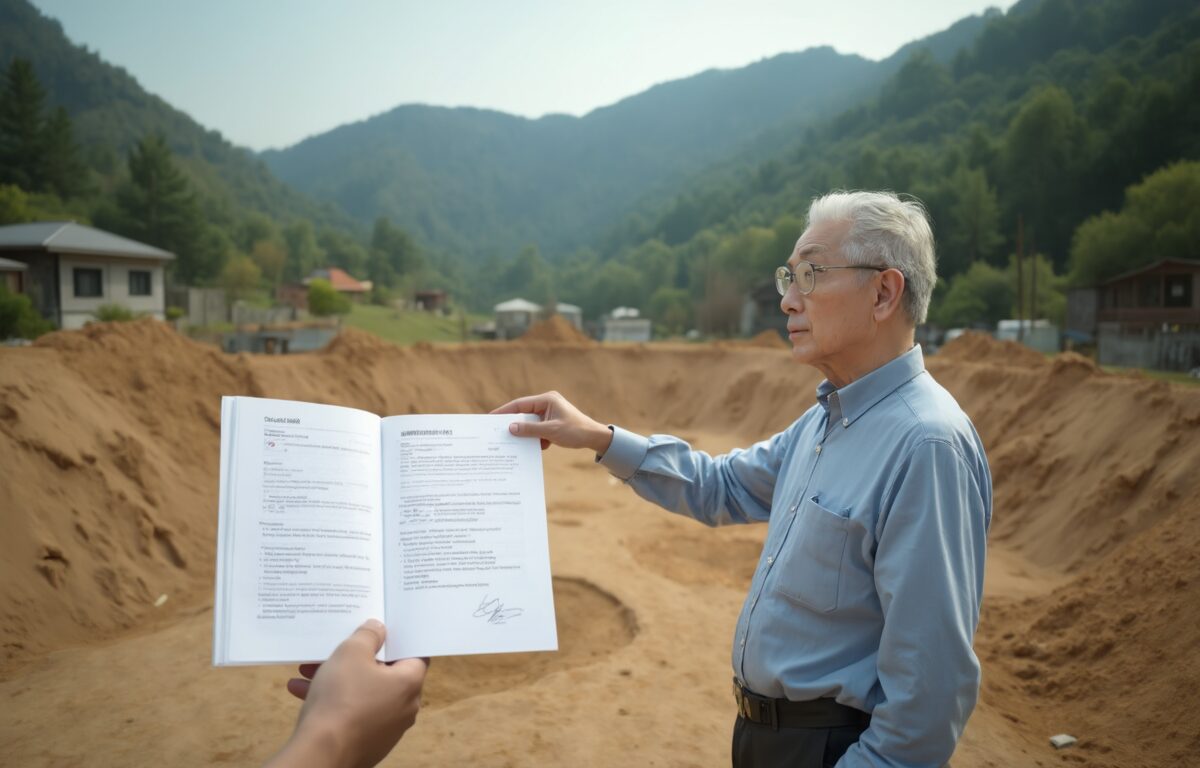
解体工事手順の最終フェーズである「解体後」は、見た目が更地になったからといって終わりではありません。
ここからが法律的にも重要な作業の始まりです。
中でも「建物滅失登記の申請」は必須。
これは取り壊された建物が公式に存在しないことを登記簿に反映させる手続きで、施主本人が法務局に対して行います。
提出期限は「解体完了から1か月以内」が原則なので、忘れると過料の対象になることもあります。
必要書類としては、建物取毀証明書や現地写真、印鑑証明書などが代表的です。
また、解体業者による産業廃棄物(ガラ)の搬出・清掃も完了したかを確認し、現地が整地された状態になっているか最終チェックを行う必要があります。
もし土地を売却したり建て替え計画がある場合、このタイミングで次工程へ進めるための調整や不動産会社への相談を開始することがおすすめです。
さらに、近隣住民への「工事完了報告」も忘れてはいけません。
騒音や振動など我慢してくれた周囲への配慮が今後の良好なご近所付き合いにもつながります。
以下は、解体工事後に施主が行うべき主要な作業一覧です:
- 建物滅失登記の申請(1か月以内)
- 近隣住民への工事完了報告
- 解体業者への支払い確認
- 土地の売却や建替えに向けた整地確認
このような流れを踏むことで、「解体工事全体フロー」の完全な完了となりますよ。
解体工事に必要な届出と法的手順

解体工事手順を進めるにあたり、最も重要かつ見落とされがちなポイントが「法的な届出」と「各種書類の整備」です。
特に延床面積が80㎡を超える建物を対象にした解体作業では、「建設リサイクル法」に基づく事前届出が必須となり、届け出を怠ると行政指導や、場合によっては罰則の対象にもなります。
また近年は、解体現場におけるアスベスト(石綿)含有建材の問題が重視されています。
すべての建物に対して事前調査報告義務が課されており、仮にアスベストが含まれている場合は、専用のアスベスト処理手順に従った分離作業と安全管理が求められます。
そのため、あらかじめ作業計画や作業手順書テンプレートを用いて、関係者全員が工程とリスクを把握できるよう情報共有しておくことも重要です。
法的手続きを適切に行うためには以下のような書類の準備と提出が求められます:
| 書類名 | 提出先 | 対象条件 |
|---|---|---|
| 建設リサイクル法届出書 | 自治体 | 延床80㎡以上 |
| アスベスト調査報告書 | 自治体 | すべての建物 |
| マニフェスト(産廃管理票) | 管理用 | 廃材発生時 |
| 作業手順書 | 作業責任者 | 全工程 |
これらの書類はただ形式上用意するだけでなく、内容の正確性と実効性が極めて重要です。
たとえば手順書の作成を怠った場合、安全性確保やトラブル時の対応に著しい支障をきたすこともあります。
したがって「誰が」「いつ」「どこで」「何をするか」を明文化し、専門業者との連携や行政との連絡にも使える信頼性あるドキュメントとして仕上げましょう。
建物構造別の解体手順と注意点
解体工事手順は建物構造によって大きく異なります。
特に木造、鉄骨造(S造)、RC造、ALC構造は工程・工期・費用に差が出るため、事前の見積もり精度にも直接影響します。
まず、もっとも多い木造住宅解体段取りについては手作業比率が高く、それにより周囲への振動や騒音は比較的小さい傾向があります。
ただし狭小地では重機が入らず全て手作業になることもあるため、追加費用が発生する場合があります。
一方でRC造解体工程になると話は変わってきます。
RC(鉄筋コンクリート)構造は強度が非常に高いため、一般的な木造と違い必ず大型重機を必要とします。
また、安全マニュアルの整備や行政への届出なども多く、工期も長期化する傾向です。
坪単価で木造が約3〜5万円なのに対して、RC造では約5〜7万円とコスト面でも差が大きいです。
鉄骨プレハブ建築などによく使われるS造解体手順では火気使用が絡むため、消防法などの厳格な安全対策を講じる必要があります。
また外装にALCパネル(軽量気泡コンクリート)を使用している場合、ALCパネル解体にはパネル単位での分別処理や産廃管理票(マニフェスト)の明確化が求められます。
以下に構造ごとの解体費用・工期や注意点をまとめました:
| 構造 | 坪単価目安 | 工期目安 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 3~5万円 | 7~10日 | 手作業比率高い |
| RC造 | 5~7万円 | 14~20日 | 重機必須・届出多い |
| 鉄骨造(S造) | 4~6万円 | 10~14日 | 火気使用あり |
| ALC構造 | 4~6万円 | 10~15日 | パネル処理が必要 |
このように建物の構造ごとに「何をどう壊すか」が大きく異なります。
それぞれの段取りを把握しておけば、不意の追加請求やトラブルも減らせますよ。
作成者の一言
「何から始めればいいのか分からない…」そんな不安を抱えていた私も、解体工事の手順を一つひとつ整理することで、安心して計画を進めることができました。解体工事は、事前準備から着工、そして解体終了後の手続きまで、段階的な進行と周囲への配慮が欠かせません。
特に印象に残ったのは、施主として事前にやるべき準備の多さと、工事中は業者に任せる部分が中心になるという役割の明確さです。また、各工程の順番を把握しておくことで、急な変更やトラブルにも落ち着いて対応できました。建物構造による違いや法的手続きまで考慮すれば、よりスムーズな進行が可能です。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。最後にひとつアドバイスをするなら、「何をやるか」だけでなく「いつやるか」を意識すると、無理なく全体を管理できますよ。時間に余裕を持って行動することが、納得のいく解体工事への第一歩でした。




